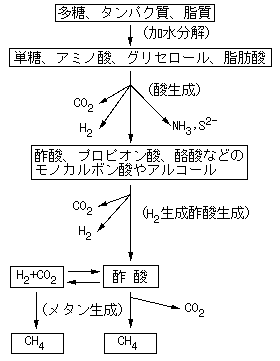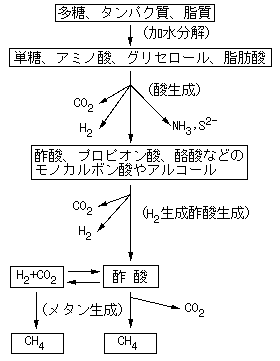
私の「環境学」をめざして
村瀬潤
環境生態学科
私は、10年にも満たない短い期間ですが、これまで土壌中の微生物の生態を中心に研究活動を続けてきました。土壌学を志したきっかけは、土壌が農産物を含むあらゆる陸上植物生息の最も基本的な場であるにもかかわらず、その重要性が国内では一般的に実感されていないことに不満を感じていたことにありました。そして、土壌中で起こる化学現象の殆どに関係しているのが肉眼では見ることの出来ない微生物であることに不思議な魅力を感じてこの研究分野を専攻しました。私の興味は、どちらかといえば世間的にはあまり日の当たらない研究対象にあったのかも知れません。
ところが近年地球環境問題が取り沙汰されるようになって、土壌が皮肉なことに悪役として注目を集めるようになりました。土壌を湛水して水稲を生育する水田では、土壌内部が酸素のない嫌気的な環境になるため、嫌気微生物の働きによりメタンガスが生成し、それが地球の温暖化の原因の一つとなっているという指摘を受けたのです。私の研究室で水田土壌のメタン生成に関する研究が始まった頃(1990年)は、限られたデータから、大気へ放出されるメタンガスの20%が水田に由来すると見積もられていました。その後、多くの研究グループが水田からのメタン放出量をより正確に推定すべく、世界各地でメタン放出速度の測定を開始しました。我々の研究グループもそれまで殆ど研究例のなかった熱帯(タイ国)水田のメタン放出速度を実測しました。こうした実測データの蓄積により、推測される水田の寄与率は数年間で当初の半分程度にまで減少しました。
海外では、メタン放出量を実測しましたが、それだけではごく表面的な現象をとらえたにすぎず、土壌中で何が起こっているかは全く理解できません。国内では水田土壌のメタン生成に関わる微生物の研究を併せて進めてきました。メタンは直接的にはメタン生成菌と呼ばれる細菌によって生成されますが、実際には多種多様な生物の見事に完成された共同作業によってメタン生成が行われているのです。
絶対嫌気性菌であるメタン生成菌は、分子状酸素はもちろん、酸化鉄や硫酸など酸素を含んだ物質が存在しても生育することが出来ません。水田に水が張ると大気から土壌への酸素の供給はほとんどなくなり、まず第一に好気性の微生物が呼吸により酸素を消費します。続いて硝酸イオン(NO3-)・二酸化マンガン・酸化鉄・硫酸イオン(SO42-)などに含まれる結合性酸素を次々に嫌気呼吸により消費してゆきます。その結果、土壌は強い還元状態となり、そこで初めてメタン発酵が起こります。もちろん、メタン生成に至るまでの好気・嫌気呼吸を支える十分量の有機物が必要となります。
メタンの起源となる有機物は、多糖類・タンパク質・脂質などの高分子物質ですが、メタン生成菌が直接利用できる基質は酢酸や炭酸ガス・水素など数種類に限られています。では、その酢酸や水素はどこからやってくるのでしょう? 先に述べた高分子物質は、まず単糖、アミノ酸などの単位構成分子へと加水分解されます(加水分解段階)。つぎに、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの揮発性脂肪酸、乳酸やコハク酸、エタノールなどのアルコール類、水素、二酸化炭素などに分解されます(酸生成段階)。さらに炭素鎖が3つ以上の揮発性脂肪酸は、酢酸と水素に分解されます(酢酸水素生成段階)。各段階には複数の異なる微生物(主に細菌)がそれぞれ関与していて、これら一連の過程をへて生成された酢酸、または水素と二酸化炭素がメタン生成菌によってメタンへと変換されるのです(図1)。このように前段階の微生物群の代謝産物は、次段階の微生物群の重要な基質となりますが、前者にとって代謝産物はいわば排泄物とも言えるもので、後者が存在しなければ自らの排泄物の蓄積によりやがて自身の生育が阻害されてしまいます。メタン生成系は、各種微生物の相互に密接な共生関係の上に成り立っているのです。この共生関係は、細菌同士に限らず、一般的には細菌の捕食者と認識されている原生動物との間にも認められており、水田土壌においてもメタン生成菌と繊毛虫類との栄養共生を確認することが出来ました。
私は、以上のような嫌気生態系の微生物の相互作用を知るにつれ、その調和と完成度の高さに感嘆し、この系が1つの生命体であるかのような錯覚を覚えました。嫌気生態系の共生は、世間一般に使われている「人と自然との共生」に代表される片利共生(あるいは寄生)とは違い、お互いに他の存在を必要としている相利的な栄養共生です。もちろん、微生物たちは系内の調和を意図しているわけではなく、利己的に生活しているにすぎません。しかしひるがえって、人類が必要としかつ必要とされている生物がはたして存在するのだろうかと自問するとき、目には見えない微小な生命がとても大きく感じます。
私の尊敬するある科学者は、外国の科学者から「神の存在を信じるか」と問われたとき、「私にとって神とは偉大なる自然そのものであり、研究は神に近づく(神になるという意味ではない)ための方法、真理の探求こそが私の宗教である。」と答えたそうです。私は、まだまだその域には達していませんが、嫌気生態系の微生物たちを知るにつけ彼らが何をか語りかけているような気がするのです。こうして考えてみると、原初的であるとされるアニミズムこそむしろ自然科学的な信仰であり、大自然の真理の中に人類が求めるべきパラダイムシフトが潜んでいるのかも知れません。
私は、1996年度より滋賀県立大学に赴任し、湖沼の微生物生態について研究を進めていくことになりました。今度はどんな微生物たちがどんな姿を見せてくれるか、楽しみにしています。これからの研究が単に科学的事実を明らかにするにとどまらず、自分自身の自然観や宗教観を作り上げる一助になればと考えています。それが私自身の「環境学」に結びついていけばいいのですが、それにはまだまだ時間がかかりそうです。
引用文献 上木・永井 編著(1993)嫌気微生物学、養賢堂
---------------------------------------------------------------------------
図1 有機物の嫌気分解過程