
下水道に関する北京市との交流
−技術支援はわが方への投資−
奥野長晴
北京市市政設計研究総院技術顧問
西安市市政管理委員会技術顧問
環境計画学科
「日本から伝えることはもう多くない」―――これは2004年11月に開催された中日水環境検討会議において中国側の発表に接した時、私の心に去来した思いである。ここ20年間に北京市は6箇所の下水処理場を建設した。数年以内に、あと8箇所の建設を予定しているという。先端を行く下水道施設がここでどんどん設計され、どんどん建設されている。最新の設計に最新の技術と思想が宿る。だから、「下水道技術に関して全世界が中国に学ぶ時代がすぐ目の前にきている」といった方が正しいのかも知れない。1980年代、日本の下水道技術が米国を越えた。その20年後、今度は中国が日本を越える。ここ20年間で、北京はここまできたのだ。この発展の一部分に私も参加した。これを私は誇りにしている。しかしそれは同時に、技術顧問として、私の役割の終りを意味する。喜びと寂しさの交錯がこの国際セミナーの後味であった。
最初の出会い
1977年文化大革命が終わった。この10余年間、大学は閉鎖、若者は農村へ下放、だから人材育成が遅れた。この空白を埋めるべく、1980年代に、政府留学生として、中国人若手技術者が大挙日本にやって来た。これはいわゆる2次日本留学ブームの先駆けである。(1次ブームは1890年代の清朝末期、日本の明治維新を学ぶことを目的とした日本留学をさす)その中の2名との出会いが、わたしにとって、中国との関わりのスタートである。かれらは北京市市政設計院に所属する職員で1人は大阪大学に、もう一人は京都大学に留学していた。1985年7月東京で開催の下水道展に私が彼らを案内することとなった。当時私は東京都下水道局に勤務していたので、留学先の大学がこの役割の適任者として私を白羽の矢の的にしたとのことであった。そのうちの1名杭世君(女性)が、京都大学での留学終了後、東京都下水道局にて研修することになった。 私も、嘗て60年代に、後進国日本から米国にやって来た貧乏留学生であった。そんな私をアメリカは町ぐるみで暖かく迎えてくれた。 若い時、外国で受けた親切は一生心に残る。それ故、今では米国が私の第2の故郷になっている。相手こそUSAではなく中国ではあるけれども、今度は私にお返しをする番がきた。職場では東京都下水道局が総力を挙げてこの研修を支援した。週末には日光や箱根など小旅行を個人的に試みた。こうして彼女との間に私の家族を含めた交流が始まっていった。
ボランタリーによる技術支援
1980年代の末、日本政府の借款を基金として、中国最初の近代的下水処理場を北京市に建設することとなった。その設計主任に上記した杭世君が就任した。(この種の施設の設計は北京市市政設計院設院の業務になっているのでこの人事に不思議はない)。多くの途上国では、外国のコンサルタントに設計を委託する場合が多い。しかし、ここ北京市は直営、つまり自分達でこの大規模下水処理場の設計に挑戦することに決めたのである。今から考えるとこれは正しい決断であるということができる。そのおかげで技術力が向上し、いまや北京の下水道技術は世界のトップに立つことができたからである。しかし当時、これは狂気の沙汰であった。東京都でさえ行政側に設計の実務を担当する能力はもうなかった。下水道に関するノウハウが皆無の組織において、「下水処理場の設計を実行するのはまず不可能」が常識であったのである。必然的に杭世君はこのプロジェクト実行に関して技術的支援を私に求めてきた。当時私は東京都下水道局に勤務していた。だから平日に公費を用いて北京に出張するわけには行かない。下水道の設計に必要なマニュアルなど図書購入費の出所もなかった。1980年代から90年代にかけて中国の為替管理は厳しく、北京側にもこのような経費負担能力がなかった。だからといって、この切なる要望を無視すれば友情が廃る。幸い東京・北京間の飛行時間は3時間足らず、航空運賃も往復5万前後、日曜日に東京を出発、月曜日の夕刻帰国すれば10時間ぐらい北京で仕事はできる。1日の休暇をとれば何とか対応可能だ。不足部分はFAXを通じて緊急の連絡はできる(まだ電子メールなんて便利な手段は出現していなかった)。このようにして手弁当の下、技術支援がはじまった。彼女は日本語が堪能である。だから表面的なことは日本語の設計基準や参考資料を読めば何とかわかる。難しいのは水面以下に隠れた本音の情報の伝達である。こんなことは設計資料には書かれていない。北京が本当に必要なのは失敗の実例のはずである。乏しい時代に試行錯誤で時間とお金を浪費するわけには行かない。前車の轍を踏む必要はないのだ。東京の下水道普及率が10%台の黎明期から、100%に到達後の衰退期に至るまで、私は多くの経験をした。その中から失敗の事例を選び出し、これを技術交流の中心に据えることとした。「水質料金制度」もその一例である。工業廃水の公共下水道への流入抑制を目的として、東京はBODやpHに基づいて下水道使用料金を設定したことがある。しかし結果は当初に意図したこととはまるで逆になっていましった。つまり金さえ払えば悪質下水を流しても許されるとの考えを工場側に与えたのである。その結果悪質産業排水の流入を受け、下処理場の運転管理が困難、汚泥の処理処分が不可能になってしまった。失敗例はまだある。それは下水処理場へ過度にコンピュター導入することによる無駄使いだ。一つの処理場だけで電算機の補修費が年間4億円もかかっていた。80年代日本の下水道事業はお金を使い放題であった。挙句の果てオバースッペックの施設を作って下水道の先進国に到達したと錯誤していたのである。これを英語で「fancy foolish」と呼ぶ。このような愚行を再生産してはならない。
第一期高碑店処理場の完成
こうしているうちに北京に第一号の処理場が完成した。1日当たりの処理能力50万トン、第2期工事が終わると、処理能力は100万トンになる。東洋では東京の森が埼処理場に次第2番目に大きい処理場である。世界に冠たる大規模施設といってよい。借款で作る施設では、外観や内装などアメニティー部分に金をかけるわけには行かない。 この第一号処理場は「建設費が小さく、維持管理費の低い下水処理場をつくる」を基本方針として設計された。基本的機能を確保しながらどこまで下水道施設をスリム化できるかの見本がここに完成した。かつて、日本の下水道施設は豪華絢爛を誇った。しかしバブルの弾けた90年代、建設コストと維持管理コストをいかに低減するかが日本でも優先課題になった。豊な時代に育った技術者に乏しい時代の設計能力がない。北京がその先生となった。これが高碑店処理場と呼ぶもものであり、中国における近代的下水処理場の原型として雛形的役割を果たしてゆく。
大学時代の交流
1995年4月、東京都庁から滋賀県立大学への異動と前後して、私は北京市市政設計研究総院の技術顧問に正式に任命された。私がこの組織における最初の外国人顧問就任したことになる。相変わらず、報酬はなし、渡航費は本人持ち、―――などボランタリー部分が残っている。 しかし滞在費は先方が負担、顧問就任のおかげでビザの交付が容易になったなど私側の負担が減少した。加えてその上に、大学の方が都庁時代よりも行動の自由度が高い。こうして、春夏冬の休み時期を中心に、年間数回北京を訪問がすることが可能となった。小講義、設計のリビュー、機械の選択のアドバイス、などがこの頃の主たる仕事であった。 2000年頃になると、北京側にも技術が蓄積され、先進国の模倣から脱却、ひいては技術開発に向かって行く。私の研究室との共同研究の開始がこのことをシンボリックに物語っている。最初の共同研究のテーマは下水処理水の再利用であった。これを卒論のテーマ化して、私のゼミの学生をこの共同研究に巻き込んだ。これは国際交流が教育にリンクしたしたことを意味する。自分の研究が外国の政府機関に関連しているという意識が学生の学習意欲をこの上なく高めた。 そして2002年12月共同研究の成果の発表会を北京市で開催した。双方の発表者2名ずつ、まことに小さい国際会議ではあったけれども、「自分の発表を異文化圏の人々に評価してもらえたことが嬉しかった」が学生の感想である。学部の学生が研究成果を北京で発表できたことは、私にとっても20年にわたる交流の成果として、大きい喜びである。この延長が冒頭で述べた中日水環境汚染防止保全会議へと繋がってゆく。2004年11月北京で開催この会議学部4回生の盛永君がポスター発表という形で参加した。極め付きは大学院学生の副指導を北京側の一人が担当してくれたことである。ボアランタリーで始めた技術指導が滋賀県立大学における教育の質を高め、さらに大学院学生の指導体制の拡大にまで発展したのである。
総括
北京市との交流20年間を通じてわかったのは「技術交流とは卓球のようなもの」である。つまり、日本での経験が中国でさらに発展し、そして日本に帰ってくる。両側を往復する間に技術や思想が洗練されてゆく。さらに「大学における私の教育プログラム充足に対して、北京との交流が果たした貢献度の大きさはかり知れない」――これもピンポン効果の一つである。私個人にとっても北京との交流は充実感実現の早道であった。 「自分が最も求められる所にわが身をおく」ことが常に男のロマンを擽っていた。大袈裟にいえば、「他国の国造りに参加すること以上の喜びは他にない」とさえ思う場面が多かった。この喜びこそボランタリーによる交流を支えた原動力である。20年間にわたる交流を通じて、中国内に老朋友的人脈もできた。私にとってこれは至上の宝物である。手弁当で続けた技術協力がこの財産を作ったと考えている。結局技術協力とは自分の側への投資に他ならない。国際化の要諦は国境と無関係に人と人との間に信頼を構築することである。これを達成することが国際協力の究極の目的に他ならない。大学においてもこの目的を達成することができる。それは留学生の引き受けである。これは国際化の時代における大学の責務でもある。

図−1 北京では唐の時代の排水路が今でも使用されている

図−2 北京における近代的処理場第1号高碑店下水処理場
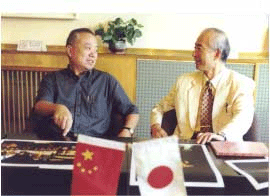
図−3 北京側と交流の打ち合わせ

図−4 北京市近代処理場第2号酒仙橋処理場長と

図−5 中日水環境汚染防止保全会議に学部4回生盛永君が参加して発表した