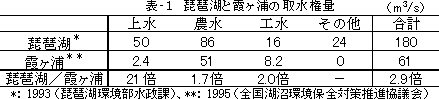
「琵琶湖周辺域の水と物質の循環」
金木亮一
生物資源管理学科
1 琵琶湖から農地へ
琵琶湖の水は、工業用水・農業用水・水道水源(生活用水)として、大量に利用されている。表-1(省略)は取水権量(取水できる権利を表すもので、農業用水は季節変化が大きいため、ここでは最大取水量を示している)を霞ケ浦と比べたものであるが、いずれの用水も霞ケ浦を大きく上回っている。特に、水道水源の量は霞ケ浦の20倍を超えており、近畿1,400万人の水瓶としての役割の大きさを如実に示している。なお、県内外の利水割合については、県外が66%と大半を占めており、霞ケ浦の15%とは対照的である。
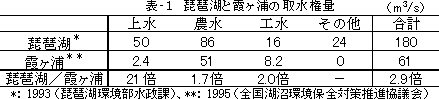
農業用水は琵琶湖の水を最も多く使用している。滋賀県の農地の90%以上は水田で、この内40%以上の水田が琵琶湖の水を灌漑用水として利用している。干拓地を除けば、琵琶湖の周りの農地は琵琶湖よりも標高が高い。水は高い所から低い所に向かって流れるが、その反対に標高が高いところに灌漑用水を送るため、琵琶湖岸には90ヵ所以上の揚水機場が設置されている。自然の水の流れとは逆向きの方向なので、これを「逆水灌漑施設」と呼んでいる。その内、比較的大きな揚水機場の受益面積と2002年度の年間総取水量は、表-2に示すとおりである。
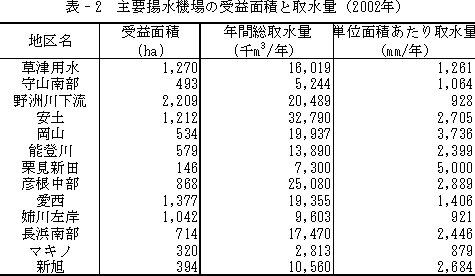
琵琶湖の周りでは最近まで、大規模な公共事業である「琵琶湖総合開発」が行われていた。京阪神の水需要の増加に応えるため、琵琶湖からの放流量を毎秒40t増やし、水位低下を−1.5mまで認める。その対策として琵琶湖周辺の保全や治水・利水の為の事業を、1972年から25年間の長期にわたり、約2兆円にのぼる費用をかけて行ってきた。当初は「開発優先」であったが、石油ショック後は「保全優先」に方針転換され、流域下水道や農村下水道など水質浄化施設の建設が盛んに行われるようになった。これによって滋賀県の下水道普及率は急激に上昇し、さらに、富栄養化防止条例(1980)によって有リン洗剤の使用も禁止されるようになった。しかしながら、毎年のようにアオコが発生しており、琵琶湖の水質は依然として横ばい状態が続いている。新たな対策の一つとして、県下の下水処理場では、多額の予算をかけた「超高度処理施設」の導入などが計画されている。
2 農地から河川へ
2.1 水量の有効利用
農地に灌漑された水は何回も再利用されている。上の水田で余った水を水路に排水せず、水田の畦畔を経由して下の水田で再利用することを「田越し灌漑」というが、このような灌漑方式は最近ではほとんど見られなくなった。その代わり、排水路や川を堰き止めて水位を上昇させ、その水を下流の水田で再利用する「反復利用施設」が多く造られるようになり、その数は県内合計で約740ヶ所にのぼっている※1)。
水田で利用される水量は1日約20mm程度。この内、実際に消費されるのは水面からの蒸発量と植物からの蒸散量で合せて5mm/日程度に過ぎず、残りは水尻からの直接流出、畦畔から排水路への浸透、田面から地下への浸透によって失われる。農家は代かきや畦塗りの農作業によって、浸透量が少なくなるように水管理を行っている。
2.2 水質の改善
点源対策に比べて、農地や道路など面源からの流出負荷削減対策は遅れており、特に、農業への風当たりが強くなっている。例えば、水田の代かき作業によって河川や琵琶湖が濁る、圃場整備事業では排水を速やかに排除したり清掃が楽になるように排水路をコンクリートで固めてしまう「三面張」にすることが多いが、これが水生植物による水質浄化を妨げているなど、多くの批判が起こっている。農業側では、濁水対策として少量の水で代かきを行う「浅水代かき」を導入したり、排水路については三面張をやめて水路底を土に戻して水生植物の生育を図るとともに、護岸は石積みなどに戻して魚の産卵・生息場所を確保する等々の改善を図っている(図-1(省略))※2)。
2.3 流出負荷の削減
汚濁物質が工場、家庭、農地などから流出する量を流出負荷量というが、流出負荷量を減らす最も有効な方法は発生源における対策である。「××は元から断たねばダメ」ということになる。流出負荷は水量と濃度を掛け算したものなので、流出水量を少なくするとともに流出濃度を低くすることが求められる。
まず、水田の水尻部から流出する表面流出量を少なくするためには、無駄な流入水を減らすことが肝心である。滋賀県ではその対策の一つとして「自動給水栓」の設置を推奨している。田面水がある深さ以下になると灌漑水が自動的に流入し、ある深さ以上になると自動的に停止するものを「全自動式」、流入は人力で行うが自動的に停止するものを「半自動式」と呼んでいる。滋賀県農業試験場のデ−タでは、半自動式の方が節水効果が高くなっている※3)。さらに、より一層の節水を図るためには、上水道のように使用水量に比例して料金を徴収することが有効である。この方式を「量水制」といい、海外の灌漑用水の少ない地域で多く取り入れられている料金制度である。日本では灌漑面積に比例して水利費(賦課金)を徴収しており、灌漑用水をいくら使用しても料金は同じであるため、節水意識が高まりにくい状況にある。
次に重要なことは肥料の削減である。水田には1ha当りN100kg前後の窒素肥料が投入されているが、稲が必要とする量はこの6〜7割に過ぎず、様々な方法で施肥量の削減が検討されている。
農地からの流出負荷を削減する第二の方策は、流出してしまった負荷を農地で再び利用すること、第三の方策は河川・内湖などが有している自然浄化機能を最大限利用することである。
滋賀県農政水産部では上記の課題に対応するため、「水すまし構想」を策定している。この構想では、「水・物質循環」を健全に保ち、農村地域からの流出負荷を少なくする種々の方法が検討されているとともに、「自然との共生」や「住民参加」の実現が目標に掲げられている(図-2)※4)。2000年度までに13の流域で、同じ流水を共有する住民が参加して「流域協議会」が結成されており、様々な学習活動や地域に密着した環境改善活動が行われている。この協議会をいかに継続・発展させていくかが、今後の課題であろう。
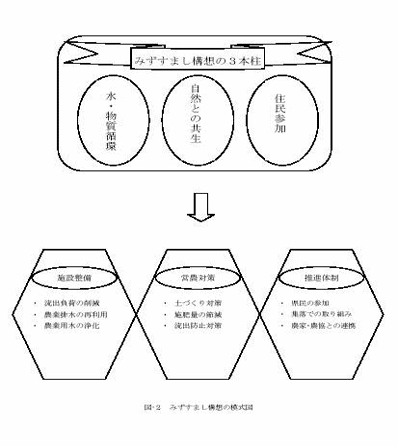
2.4 新農法による水田流出負荷の削減
2.4.1 被覆肥料を用いた育苗箱全量施肥栽培※5〜10)
最近注目されている施肥量の削減方法として、「被覆肥料を用いた育苗箱全量施肥」がある。被覆肥料とは、肥料を溶けにくい物質でカバーしたもので、カバーには水蒸気が通過する程度の微細な穴が開いており、水蒸気を吸収して内部圧が高まると肥料がゆっくり溶け出すように設計されている。この被覆肥料は育苗箱に入れて田植と同時に水田に施すことが出来る。水稲が全生育期間中に必要とする量の窒素を育苗箱に入れてやると、追肥や穂肥など水田に入って施肥する作業が不要になり、農家の労働時間の減少に繋がる。また、稲の根が肥料を抱きかかえる形で田植えされることから肥料効率が高くなり、窒素施肥量を通常の6割に削減しても収量に大きな差は生じず、水田から流出する窒素量も大幅に減少させることができる。さらに、玄米中のタンパク質含量が少なくなって食味が向上するなど一石四鳥の効果が知られており、全国的に急速に普及しつつある。被覆肥料には省力化、窒素肥料の節約、流出負荷の削減、食味の向上という一石四鳥の効果があるものの、欠点もある。1つの欠点は価格で、通常の化成肥料より5割程度高い。もう1つは、被覆材が分解し難いことである。トウモロコシから作ったプラスチックのように、土壌中の微生物によって分解されやすい被覆材も開発されているが、高い特許料をアメリカの企業に払わなければならないため一層高価になってしまうこと、窒素溶出量のコントロ−ル技術が未完成であることなどから、今のところ採用されていない。しかし、被覆材が分解され難いと、農地から流出して琵琶湖などに滞留してしまう。肥料メ−カ−は、生物分解性の被覆材を早急に使用すべきであろう。
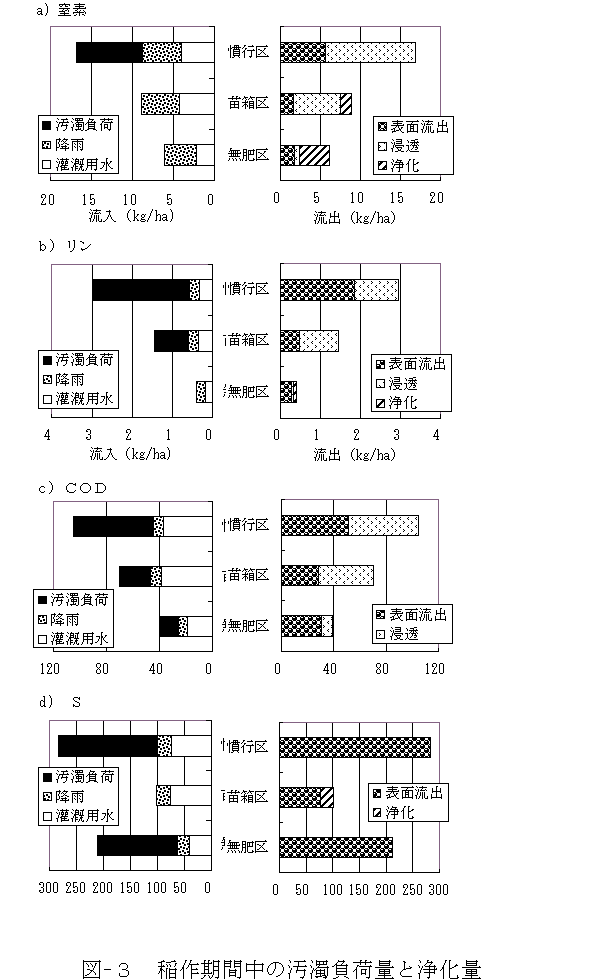
図-3※7)は、本学の圃場実験施設において3つの区を設け、水稲作付期間中の負荷量を測定した例である。ここで、苗箱区とは、無代かきおよび被覆肥料の育苗箱全量施肥を行った区である。また、慣行区とは、通常どおり代かきを行い化成肥料を施用した区である。流出負荷(表面+浸透)が流入負荷(灌漑用水+降雨)を上回る場合は「排出型水田」※11)と呼ばれ、汚濁負荷が水田から発生したことになり、逆に、流入が流出を上回る場合には「吸収型水田」※11)と呼ばれ、水田で浄化作用を受けたことになる。慣行区では窒素、リン、COD、BOD、SSの全てで「排出型」になっており、窒素8.2、リン2.4、COD 60、BOD 14、SS 190kg/haの負荷量を排出している。全国の単位水田35ケ所の調査事例※11)によると、窒素の差引排出量は-17〜+18kg/haの範囲であり、本実験ではその範囲内に収まっているものの、事例の平均値+3kg/haに比べて多めになっている。これは、灌漑用水が琵琶湖の水で窒素濃度が低いため、水田の窒素浄化能が発揮されにくかったためである。一方、リンの差引排出量は全国34ケ所の調査事例※11)によると-3.0〜+1.7kg/haであるが、ここではそれを上回る排出量になっている。これは窒素と同様に灌漑用水のリン濃度が低いこと、および、土壌中に残存しているリン肥料成分量の差異によると考えられる。
これに対して、苗箱区ではリン0.84、COD 23、BOD 10kg/haの「排出型」になっているが、量的には慣行区の35〜71%に減少している。一方、窒素とSSについては1.4と25kg/haの「吸収型」となっている。苗箱区において窒素が浄化されたのは、無代かきと育苗箱全量施肥の2つの効果によるものであり、SSが浄化されたのは無代かきの効果である。一方、無肥区では窒素、リン、BODが浄化されているが、CODとSSで汚濁負荷の流出が起こっており、代かき・移植期のCODとSSの流出負荷量が多かったこと、水田でプランクトンなどが内部生産されたことを反映している。
2.4.2 無代かき移植栽培※12〜14)
「不耕起移植」と「無代かき移植」は、代かきに伴う濁水発生を防止するための、有力な方法の一つである。不耕起は収穫後の耕起や代かきを全く行わず、稲株が残ったままの状態で苗を移植する省力的な農法で、八郎潟干拓地で盛んに行われてきた。濁水対策としては非常に効果的だが、雑草が繁茂して除草剤の使用量が増える可能性が高い。これに対して、無代かきは耕起を行って雑草の根を切るため、除草剤の使用量は増えず濁水も生じ難いことから、八郎潟では不耕起よりも無代かき移植を採用する農家が増えている。ただし、代かきを行わないと地下浸透量が多くなって水管理労力が増す場合があり、砂質の水田にはあまり適さない。粘質な水田、特に琵琶湖周辺の低平地に薦めたい農法である。
3 河川から内湖へ
3.1 内湖の数と面積
内湖は琵琶湖の周辺にある小さな湖の呼称であり、琵琶湖と水路で結ばれていることから、琵琶湖の水位変動の影響を受けるのが特徴である。第二次世界大戦以前には約40ヶ所3,000ha以上存在していたが、戦後の人口増加と食糧不足に対処するため、多くの内湖が干拓されて農地に替わることになった。1944〜71年の間に、国および県の事業によって16ヶ所2,500ha余が干拓され、現存する内湖の数は23ヶ所、総面積432haにまで減少している(図-4)※15。なお、1985年〜90年にかけて人工の内湖が10ヶ所出現している。環境保全対策によるものだろうか?否である。琵琶湖総合開発によって湖周道路が建設され、琵琶湖の一部が道路によって琵琶湖と切り離された結果、内湖状態になったものである。
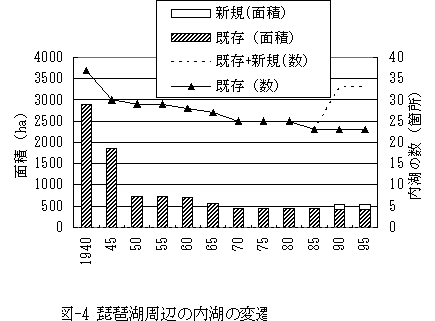
干拓とは、水面や低湿地などを堤防で締切り、内側の水を排水して新たに陸地をつくることである。干拓地は琵琶湖の平均水面よりも標高が低いため、ポンプ場を設置して干拓地に降った雨水や農地からの排水を、琵琶湖に排出している。早期に干拓された内湖は主として水田として利用されてきた。しかし、コメの一人当たりの消費量が減少し、豊作などもあってコメの備蓄量が多くなると、1970年からは「コメの減反政策」が始まり、水稲の作付面積が制限されるようになった。例えば、近江八幡市の津田内湖干拓地においては、国がコメの増産を目的として干拓したものの、干拓後に水田として利用することを禁止されて畑作利用に限定され、農家の高齢化や後継者不足もあって、半分以下の面積しか利用されていないのが現状である。
3.2 内湖の水質浄化機能
内湖には大別して3つの浄化機能がある。1つは、沈殿などによる物理的浄化。大雨が降ると、道路や屋根に堆積した泥などが河川に流出する。河川の底にも泥が溜まっているが、これも流速が早くなると巻き上げられて一緒に流下する。大雨のときの川が黒褐色に濁っているのは、泥の色を反映している。ところが、川から内湖に流入すると、内湖では川よりも幅が広く水深も深いため、流速が遅くなる。押し流されてきた浮遊物質の一部は重力によって沈降し、内湖の底に堆積して底泥となる。
2つ目は化学的浄化で、こまかい粘土やイオンが凝集すると沈殿しやすくなり、土粒子に吸着しているリンなども同時に除去される。
3つ目は生物学的浄化で、内湖の周辺や湖面に生育しているヨシやヒシなどの水生植物、植物プランクトン、水生植物の茎や湖岸の石などの表面に生息している微生物膜によって、窒素やリン、有機物が分解吸収される。
近年、この水質浄化機能に関心が高まり、河川に沿って内湖を造成したり(守山川下流など)、干拓された内湖を再びもとの姿に戻す動きが見られる。琵琶湖の水質が横ばい状態で回復の兆しがなかなか見られないため、内湖の水質浄化能が見直されているわけである。びわ町と湖北町にまたがる早崎干拓地の一部は既に内湖に復元され、水質浄化能の測定※16)や水鳥、水生動植物の調査が行われており、近江八幡市の津田内湖干拓地でも復元の運動が起こっている。しかし、内湖を復元しても自然状態に放置したままでは、浄化能におのずと限界がある。農地として使われていたところでは、多量の有機物、窒素、リンが残留している。湛水によって土壌は酸欠状態になり、特にリンは水中に溶け出しやすくなる。窒素についても、一部は脱窒菌によって窒素ガスに替えられて大気中に放出されるが、一部は水中に溶け出して内湖の窒素濃度を上昇させる。農地を内湖に復元しても、数年間はSS(土粒子やプランクトンなどの懸濁物質)や有機物(BODやCOD)、窒素、リンの汚濁源となる可能性があることを、覚悟しなければならない。
3つの浄化能の内、最も浄化量が多いのは沈殿で、特に降雨時に高い浄化量が観測されている。表-3※17)は、本学近傍の野田沼内湖で、水質浄化能を測定した例である。降雨による内湖への流入水量の増加が見られた場合(降雨時)と降雨の影響の見られなかった場合(晴天時)の平均浄化量を比べると、いずれの物質も降雨時の方が多くなっている。これは、降雨に伴って面源からの流出負荷や河川に堆積した底泥の巻き上げ量が増大し、内湖に流入する負荷量も増加したためである。内湖に流入した負荷は沈殿や植物による吸収などによって浄化される。流入水量の増加に伴って内湖の底泥の一部も巻き上げられて内湖から流出するが、それよりも浄化される量の方が多いことを示唆している。降雨時と晴天時の平均値の差をt検定したところ、BODとT-Nでは高度に有意な差(危険率1%)を示し、SSとT-Pでは有意な差(危険率5%)を示している。また、灌漑期の晴天時と非灌漑期の晴天時を比較すると、いずれの水質項目についても灌漑期の浄化量が多くなっている。灌漑期には非灌漑期に比べて流入負荷量が多くなるためである。
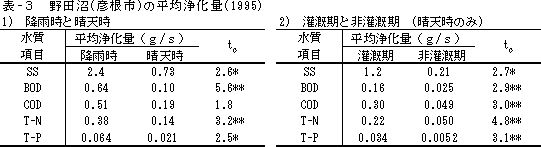
大雨に伴う出水の初期には、道路や河川に堆積していた汚濁物質が一気に流れ出す。この現象をファ−ストフラッシュといい、水質の濃度が急激に増加する。このファ−ストフラッシュを内湖に流入・滞留させることができれば、飛躍的に浄化能が向上する。ただし、年々底泥の堆積が進んで内湖が浅くなると、風による波や少量の降雨によっても底泥が巻き上げられ、内湖から流出するようになる。また、内湖に生息している水生植物は秋から冬にかけて枯れて流出し、BODやCOD、有機態窒素・リン濃度の増加を招く。
これらの悪影響を除くためには、維持管理作業が必要不可欠になる。昔は、内湖の底泥をすくい上げたり、水生植物を堆肥化して水田の肥料として使っていた。しかし、今では安価な化学肥料の普及や農家の減少・高齢化に伴って、底泥は全く利用されなくなり、廃棄物として埋立地などで処分されている。浚渫工事をすれば浄化能は一時回復するが、多額の費用が必要となる。浚渫された底泥を水田に還元できなければ、廃棄物と化してさらに処理費用が嵩むことになる。そこで、農村地域における物質循環を促す必要がある。水生植物や底泥、ワラ、畜産廃棄物、生ゴミなどを集積し、農地や家庭菜園で手軽に利用できる有機肥料に変える「地域ぐるみのシステム」を創り出すことが、内湖再生の鍵となろう。
4 内湖から農地へ
琵琶湖岸に近い水田では下流に水田が少ないため、その排水はほとんど再利用されずに、そのまま琵琶湖に流出してしまう。排水中には土粒子などの懸濁物質や有機物、肥料成分が含まれているため、琵琶湖の水質に直接、悪影響を及ぼすことになる。この対策として、琵琶湖に流入する直前の排水路の水を逆水灌漑施設に導き、ポンプで上流の水田に戻すことが行われている。水田に戻された排水は、稲に吸収されたり土壌生態系によって浄化され、琵琶湖に到達する汚濁負荷量の減少に寄与している。

循環灌漑施設で再利用される水源としては、近年、内湖が注目されるようになった。従来の循環灌漑施設の大部分は、排水路の水を再利用している(表-4)※18。排水は濁っており、土粒子の混入によって揚水ポンプが傷みやすくなるとともに、ビニールや発泡スチロール、生ゴミなどが取水口のスクリ−ンに集積してしまい、その除去・処分に多大な労力と費用がかかるため、再利用率は年々低下している。内湖を利用する場合には、あらかじめ土粒子の大部分が沈殿除去されるため、循環灌漑に対する障害は少なくなる。今のところ県内数ヶ所の内湖が循環灌漑に利用されているだけであるが、今後の増加が望まれる。ただし、ゴミの削減については、地域住民の協力が必要不可欠であることは言うまでもない。
引用文献
1) 金木亮一(1991):反復利用水の水質と水田による水質浄化効果、農土誌59(11)、31-36
2) 端 憲二(1998):水田灌漑システムの魚類生息への影響と今後の展望、農土誌66(2)、15-20
3) 滋賀農試他(1985):琵琶湖−淀川水系における農業排水の水質改善に関する研究、85-118
4) 滋賀県農政水産部(2000):農村地域の環境対策必携
5) 金木亮一、久馬一剛、岩間憲治、小谷廣通(1998):無代かき移植・育苗箱全量施肥栽培法による表面流出負荷削減効果、農土論集196、183-188
6) 金木亮一、久馬一剛、小谷廣通、岩間憲治(1999):育苗箱全量施肥が流出負荷および収量・食味に及ぼす影響、農土論集201、73-79
7) 金木亮一、久馬一剛、稲垣ちずる、小谷廣通、須戸幹(2000):無代かきおよび育苗箱全量施肥栽培水田における流出負荷量の削減、土肥誌71(4)、502-511
8) 金木亮一、久馬一剛、白岩立彦、泉泰弘(2000):無代かきおよび育苗箱全量施肥栽培水田における水稲の生育、収量、食味と窒素、リンの収支、土肥誌71(5)、689-694
9) 金木亮一(2000):琵琶湖の水質保全と新農法、農土誌68(12)、 39-42
10) Kaneki, R.(2003):Reduction of effluent nitrogen and phosphorous from paddy fields、Paddy and Water Environment、 1(3)、 133-138
11) 田淵俊雄・高村義親(1985):集水域からの窒素・リンの流出、p.80、東京大学出版会
12) 金木亮一、高橋紀之、矢部勝彦(2001):代かきの有無および肥料の種類が田面水の窒素・リン濃度に及ぼす影響、農土論集211、29-34
13) 金木亮一、岩佐光砂子、矢部勝彦(2001):田面水のSS・COD濃度に及ぼす代かき、施肥および土壌の種類の影響、農土論集215、43-48
14) 金木亮一、矢部勝彦、小谷廣通、岩間憲治(2002):田面水の窒素・リン濃度に及ぼす代かき、施肥および土壌の種類の影響、土肥誌73(2)、125-133
15) 滋賀県(2000):マザ−レ−ク21計画 琵琶湖総合保全計画
16) 大道暢之、金木亮一(2003):湿地における水質浄化機能、平成15年度農土学会大会講演要旨、198-199
17) 金木亮一、中村正久、泉峰一、姫野靖彦(2003):内湖と循環灌漑による水質浄化、農土誌71(9)、31-36
18) 金木亮一(1989):循環灌漑による琵琶湖への流入負荷削減効果、農土誌57(7)、39-44