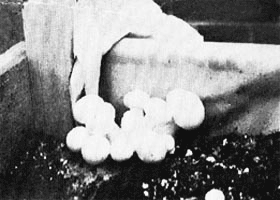菌を通して生物を見る−応用菌学から環境菌学ヘ
鈴木雄一
生物資源管理学科
芝生にはきのこがよく似合うと僕は思う。しかし、きのこの防除の農薬さえ開発されていたようで、悲しいことに我が国では事情は違うようだ。ハラタケが草地に形成するきのこの輪(フェアリーリング、妖精の輪と訳される)をかねがね見たいと思っていたが、今年はあちこちの芝生でそれを幸運にも観察することができた。シャンツとピーマイゼルの今世紀初頭の研究が明らかにしたように、芝生に波打つ緑の濃淡はハラタケによる栄養成分の供給の変化を示し、その地下の大きな活動を暗示するものである(図1)。
ところで、我が国はきのこの栽培が盛んであるが、その様相は他の地域とは趣を異にしている。世界でもっとも生産量が多いのがツクリタケやフクロタケのような里のきのこであり種類も限られているのに対し、わが国で栽培されるきのこの種類はシイタケ、エノキタケ、ナメコ、ブナシメジ、ヒラタケ、タモギタケ、オオヒラタケ、マイタケ、ヤナギマツタケなど木材腐朽性の山のきのこである。さらにトキイロヒラタケ、エリンギとよばれているヒラタケ属の一種、ハタケシメジなど続々と新しい種類が加わっている。これらはおがくずと米糠をびんや袋に詰め殺菌する方法で栽培される。もともとは森本彦三郎氏によって未利用資源を利用した栽培として昭和初期に開発されたものだが、現在ではおが屑もわざわざ製造するような時代になってしまい、先達森本氏の思いから遠いものになってしまったように思う。
そもそも、きのこ栽培は副産物から食料を得るという資源利用の一形態として発達した。また、殺菌を行わなくても、それに替わる過程が自然のしくみとして存在していた。「かれらは巣の中央にきのこの培養床をつくり、パリ近郊の昔の地下採石場における食用ハラタケ(ツクリタケのこと、筆者注)のスペシアリストのように方法的に茸を育成する」というメーテルリンクのキノコシロアリの描写には昆虫と人間の行為が重なって見える。技術が進んだ現在でもマッシュルームやフクロタケの栽培において自然の発酵熱により微生物相を安定化させ、目的のきのこを優占的に増殖させるという技術の基本原理は変わっていない。また初期のシイタケ栽培は鉈目式とよばれ、ほだ木に傷を付けて自然の胞子による感染の機会を待つというものであった。いっぽう、現在のわが国のきのこ栽培は無菌設備と殺菌技術という近代技術への依存度を高めた、実験室的な手法となっており、見方によっては必ずしも進んだ方法とはいえないのではないだろうか。というのは、環境から生物を隔離することによってなりたっているからである。伝統的な醗酵技術は、ごく普通の環境で目的の菌の増殖を可能にしており、バイオテクノロジーのひとつの到達点となりうるものである。
ところで、環境がキーワードとなった90年代に世の中には抗菌加工の製品があふれるようになったのは不思議な感じがする。僕たちは菌類の胞子の飛び交うまさに菌の中に暮らしているのである。木材腐朽菌としてよく目につくスエヒロタケが肺に生えることが話題となったが、免疫の働きは僕たち自身のなかにあり、僕たちは菌と共存しながら平和に生活していることのほうが多いのである。
というわけで僕は次のようなことを課題としたいと考えている。ひとつはきのこの生産を原点である資源の利用型にもどすこと、そしてもう一つは殺菌をしないですむ大量培養技術を確立することである。これまでの研究からどうやらこの2つのことがらは、独立したものではなく、ひとつのこととして解決できそうな感触を得ている。
たとえば、小麦わらやコーヒー粕など限られた材料ではあるが、無殺菌で菌糸を混合するという簡単な方法で、ウスヒラタケ、トキイロヒラタケなどの栽培が、大きな規模で可能となりつつある(図2)。また、今のところきのこ栽培にはほとんど使用されていないおがくずを含む畜舎敷料がツクリタケ栽培に使用できることがわかり、家畜の飼育環境の浄化技術と食糧生産の複合技術に高めていきたいと考えている(図3)。殺菌するとわらでも堆肥でも、たいていのきのこが増殖する。このことは合成培地が広範な菌類の培養に使用できることからも明らかである。これに対し、もし殺菌しないと増殖するきのこの種類は限られる。これは基質環境特異性ともよべるもので、基質の環境ときのこの間に相性が存在することを意味する。菌の嗜好性という動物的な表現も出来るかも知れない。
よく考えてみれば、自然界でのきのこの発生状況はかなり限られており、それに科学的な説明を与え、再現性のある増殖技術としてよみがえらせることは意味があるものと思われる。したがって、これまで普通に行われている、菌を分離して実験室に持ち帰って、その菌を研究するというやり方だけでなく、環境と菌を一体のものとしてとらえる見方を加えることにより、応用が環境という意識に生まれ変わるのではないだろうか。僕は学生時代よりリグニン分解性の担子菌による未利用資源の飼料化に取り組んできたが、この分野で数多くの研究がスクリーニングの結果を実用化に生か・せなかったのは、実験室では環境の影響を取り除けても、実用規模の状態では環境の大きな影響が作用するということの無理解の結果であり、僕自身はスクリーニングを行わず、野外調査に徹したことは結果として意義があったのだと考えている。
大学のキャンパスにも種類は少ないがきのこが発生し、目を楽しませてくれている。芝生のキコガサタケやホコリタケ、樹木の根元のコムラサキシメジやフミヅキタケなどである。これらはおそらく芝生や樹木に施されたバーク堆肥など有機質に由来するものであり、キャンパスの植物の成長を手助けすると同時に、菌類の研究に欠かせない勉強材料となってくれてありがたいことである。いずれ菌類の遷移も進み、腐生菌だけでなく菌根菌も現れることだろう。モンゴルの移動式住居、ゲルのまわりに、もしめん羊などの動物が歩き回るとしたら、オニフスベやハラタケなど放牧地の菌類が増えることだろうと想像をめぐらしている。
生物界がモネラからプロチスタを経て植物、動物、菌類の3方向へ進化したとするホイタッカーの5界説は多くの生物学の教科書に記されており、植物と動物の二界を提唱したリンネの罪がつい強調されがちである。しかしよく考えてみれば、分類の結果ではなく、生物の原型からの進化という概念こそが新しかったのである。「すべての生物は一なる存在ではなく、多からなる存在である」というゲーテの表現のように生物界の連続性に改めて価値を強く感じる。環境科学部も細分化された学問分野の集合体ではなく、自然な連続性の感じられる教育研究組織となることを期待している。
フィールドワークという講義では、応用するにはまずその自然の姿を知るべしと、きのこの生育環境の観察をはじめている。きのこの観察からきのこ自身が資源をどう利用しているのかを知り、その上で応用研究にとりくんでいきたいと思うからである。菌を通して生物を見るという視野にたった応用研究、これが僕のめざしている菌学の一分野であり実験室と野外との往復を欠かさずに研究を行って行きたい。これを環境菌学へと発展させることが僕のひとつの夢である。
---------------------------------------------------------------------------
図1 芝生にできたハラタケの菌輪(1996年7月12日、筑波市の農水省畜産試験場構内)

図2 無殺菌培養法により発生したウスヒラタケ(1994年5月、滋賀県立短期大学附属農場)

図3 畜舎おがくず敷料から発生したツクリタケ(1996年5月、京都市の森本養菌園)