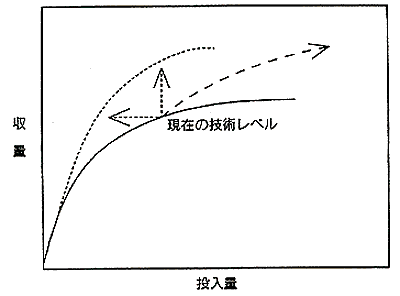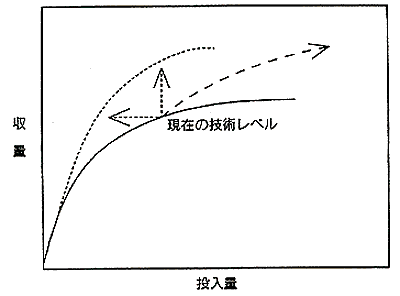
作物収量と資源投入
白岩立彦
生物資源管理学科
1970年ノーマン・ボーローグ博士は、コムギ生産の飛躍的向上に寄与した多収品種育成の功績によりノーベル平和賞を受賞した。新しい品種は耐肥性が格段に優れ、多肥栽培を可能にしたことが増収をもたらした。1960年代から70年代にかけては、そのような多肥多収を核とする近代的作物生産技術によるいっそうの食糧増産の可能性が確信されていた。ところが1980年代頃から近代農業のゆがみがさまざまな角度から指摘され、肥料の効率的使用が強く求められようになった。
飛躍的増収に寄与したコムギとはメキシコ矮性コムギであり、1950年代後半に登場しその後メキシコに設立された国際トウモロコシ・小麦改良センターが中心となって世界的に育成・普及が進められた。稲作分野でも国際稲研究所(フィリピン)によって開発された半矮性稲品種が東南アジア諸国に急速に普及した。多収品種の普及を中心とする農業技術の革新は"緑の革命"と呼ばれ、アジアやラテンアメリカ地域における食糧供給に大きく貢献した。
新品種による増収の最大の要因は、作物の耐肥性向上にあるといわれている。作物の単収(単位圃場面積当たりの収量)は、窒素をはじめとする養分の植物体への供給量に強く規制される。ところが当時までの栽培品種は近代品種に比べて草丈が高く、肥料を多く用いると栄養生長がさらに助長されて倒伏や場合によっては稔実の低下によって減収をきたしやすい。そこで短稈化をはじめとする品種改良によって、多肥条件における耐倒伏性と収穫係数(全植物体重に対する子実重の割合)が向上し、多収化が実現したわけである。
このような流れの中で、1950年からの30年間の世界の穀物生産量は約2.5倍に増加したが、その間の肥料投入量はおよそ8倍にも達した。つまりごく最近までの多肥による食糧増産過程は肥料効率の著しい低下をともなっていた。同時に農業部門で消費される全エネルギーも増加の一途をたどってきた。産業が高度に発達したわが国においてさえ現在のエネルギー総消費量のおよそ2%を農業生産が占めている。ある試算によれば、その5分の1(世界の場合の推定は3分の1)は肥料製造、主として窒素肥料の生産によるものである。もちろんこれは、食糧生産の不可欠性からみて短絡的に批判されるべきでない。しかし資源エネルギーの有限性や温暖化をはじめとする地球環境悪化への懸念が背景となって、農業生産のさらなる発展を現在までの技術進歩の延長線上に求めることは疑問視されている。
また、欧米で深刻となっている硝酸イオンによる地下水汚染は多肥農業による環境汚染の典型であり、近年のそれらの地域での環境保全型農業の推進を促す動機の一つとなった。
さらに、作物体の窒素栄養が高まると病虫害に侵されやすくなることが経験的によく知られている。またイネや麦などの穀物栽培では現在の品種を用いても肥料の過剰な投入は倒伏を招く原因となることがある。これらの障害要因は、結果として生産効率のみならず場合によっては収量自体を著しく低下させることになる。病虫害の発生に対してはもっぱら農薬による防除に依存し、また近年では倒伏防止のために植物生長物質を用いることもある。窒素肥料の多投入が新たな化学資材の投入の必要性を招くわけであり、効率面や周辺の生態系に及ぼす影響の面から考えると好ましいことではない。
これらの問題が指摘される一方、世界の人口増加による食糧の絶対的不足が近い将来予測されている。しかも耕地面積の拡大には限度があるので、世界的な単収の向上が必要とされている。農業は、有限な資源・エネルギーの浪費をできるだけ抑え農業生産と環境との調和を復活・維持しながら、なおかつ急増する食糧需要に応えなければならないという困難な課題に直面している。
このような状況のもとで農業技術開発には方向転換が求められているように思う。つまり、投入量の増大にはあまりこだわらずに増収をもっぱら指向してきた従来の方向から、インプットに対するアウトプットの量を高める方向への転換である。図はそれを概念的に示したものである。実線が現在の技術レベルにおける投入量・収量曲線を表わすとすると、破線の矢印は投入の新たな増大が確実に増収に結びつくような従来の技術発展を指す。これは収穫漸減則の克服と呼ばれる。一方横向きおよび縦向きのベクトル(点線)は、投入量当たりの生産量を高めることによって収量を維持しながら資源・エネルギーの消費をできるだけ抑えようとしたり、投入しうる資源が制限される場合の生産キャパシティの向上をはかるという方向を表わす。例えば筆者が研究対象にしている窒素施肥に関して言えば、作物体が利用可能な単位窒素量当たりの生産量もしくは収量(以下、窒素利用効率)を高めることが必要となる。
窒素利用効率はさらに、次式のように2つの側面に分けて考えることができる。
式右辺の前の項は窒素吸収効率、後の項は吸収窒素当たりの生産効率と呼ぶことができる。これらは多肥農業のゆがみを是正するうえでそれぞれ異なった意味を持っている。
窒素吸収効率の向上は、言うまでなく効率的施肥を可能にし経営改善に直接結びつき、過剰な栄養分の系外流出の制御にもつながる。一方、吸収窒素の生産効率は、植物組織の窒素濃度が種固有の範囲に収れんする傾向があることから明らかなように、本来安定的なものである。しかし、仮に1ないし2割程度の変動しかみられないとしても、それは栽培上無視できない意味が持つ。例えば水稲の場合、窒素栄養が過剰になると、倒伏による減収が引き起こされるほか、病虫害が相対的に発生しやすくなる。しかもそれは堆肥のような有機質肥料を用いた場合も例外ではないことがわかっている。
以上のような認識のもと、筆者は現在、水稲の窒素栄養と収量生産との量的関係について種々検討しているところである。
---------------------------------------------------------------------------
図 栽培技術検討の視点(概念図) 破線:従来の方向(収穫漸減測の克服)点線:新しい課題