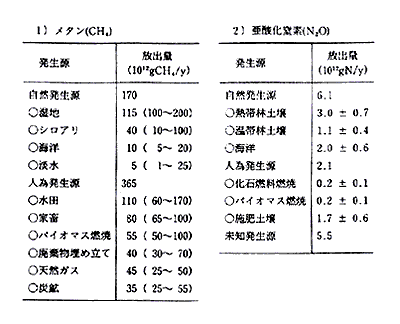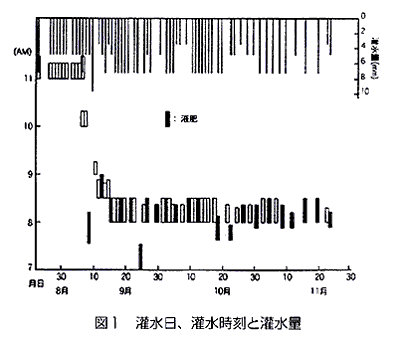
環境科学部の中の水資源利用学
小谷廣通
生物資源管理学科
水資源利用学は、従来の学問体系の中では、農学の分野における灌漑排水学の灌漑に相当する。灌漑とは、自然の水循環を補完し、人為的に農地の水環境を制御することと定義されている。そして、その目的は、高度な生産性を有する農地にするため、作物の生育と農作業に好都合な水環境を創出することにあるとされている。この灌漑の目的は現在でも維持され、今後も保持されるべきことに大きな疑問はないと思われる。
しかし、従来の作物栽培体系は、現在でも、環境保全についてはあまり考慮せずに確立された生産性重視の体系と思われる。このため、農業の分野が地域や大気の環境問題と深い関わりをもつに至ったことは否定できない。これに関連して、次に、作物栽培体系の中で圃場の水管理方法を取り上げ、これと地域や大気の環境問題との関わりを見てみよう。
まず、琵琶湖の水質保全という観点から、水管理と地域環境保全との関わりを見てみる。筆者は、以前、県内のハウス抑制キュウリ栽培における水管理と施肥管理の実態調査を行った(図1参照)。ハウス抑制キュウリ栽培では、多収を目的として多肥栽培される。この結果、土壌表面に塩類が集積し、塩害が生じる危険性があるため、多量の水が灌漑される。こうすると、土壌は湿潤状態が持続されるから、肥料分は水とともに地下に浸透する。これでは、作物に栄養分が十分供給できないので、さらに施肥が追加される。このような施肥管理と水管理のアンバランスによって、地下に浸透する無効な肥料分や水分が少なくないことを実態調査から明らかにした。施肥後無効となった肥料分は、水とともに移動するから、水循環と同様の過程を経るものと考えられる。すなわち、土壌中に貯留(土壌による吸着)されたり、土壌微生物によって分解されたり、また、大気へ放出されたりする。さらに、湖沼(琵琶湖)や河川に流出して水質汚濁の原因となる。この調査結果は、県全体の施設園芸における施肥管理と水管理の実態を表すものではない。また、水田作や露地畑作の両管理はこれほど極端には行われていないと思われる。しかし、いずれの場合も、琵琶湖の水質保全にとって不都合な影響を与えているものと推測される。
次に、圃場の水管理と大気環境保全との関わりを見てみる。農地からは、メタンや一酸化二窒素のような地球環境問題(地球温暖化およびオゾン層の破壊)と関連が深い気体が放出されている。メタンの地球温暖化に対する寄与率は15〜20%程度と大きい。そして、メタンの種々の発生源の中で、水田からの放出量は大きく、全体の15〜20%程度と推定されている(表1参照)。水田からのメタンは、還元層において、土壌微生物が有機物を分解する過程で発生する。還元層の生成は、圃場の水管理(湛水灌漑)に起因する。湛水条件下で水稲を栽培する目的は、(1)十分な水の供給、(2)雑草防除、(3)連作障害の回避、(4)温度調節、(5)地力の消耗抑制と肥料分の供給などがあげられている。このように、水田の水管理は、現在でも生産性を重視して行われている。ところで、この湛水灌漑は、一般的に、全栽培期間実施されるわけではなく、中途で中干しと呼ばれる湛水しない期間が設けられる。中干しの栽培学的意義は別にあるが、これによってメタンの発生が大きく抑制されたと報告されている。また、一酸化二窒素の場合には、自然発生源と未知発生源からの放出量が大部分を占めるが、人為発生源からの放出量は農地(施肥土壌)がほぼその大半を占めると推定されている(表1参照)。現在のところ、地球温暖化に対する一酸化二窒素の寄与率はそれほど大きくないが、年々増大するものと予測されている。農地における一酸化二窒素は、施用された窒素肥料が土壌微生物によって硝化および脱窒される過程で発生する。一酸化二窒素の放出と水管理との関係では、湛水するよりしない方が、また、間断日数(灌漑の間隔)の長い方が、これの放出量は大きいと報告されている。
以上のように、農業は、地域および大気の環境保全と深い関わりを持っており、保全対策として、窒素肥料の抑制、また、有機物の施用方法および水管理方法の改良などがあげられている。水管理方法については、上で述べたことから推察すると、水田では間断灌漑が、畑地では少量ではあるが多数灌漑する方法(少量多数灌漑)が有効であると思われる。現時点では、農業における保全対策が最優先課題になっているわけではない。そして、言うまでもなく、地域および大気の環境保全には地域全体あるいはグローバルな視点からの総合的な対策が必要である。しかし、上に示した水管理方法の改善などによる保全効果が小さいとしても、それぞれの分野で最大限の保全対策が検討されるべきであろう。
以上のことから、今後の作物栽培体系は、生産性と地域および地球環境保全とが調和するように再構築する必要があろう。今までの灌漑技術は、従来の栽培体系を前提とした上に確立されてきたと思われる。したがって、環境科学部の中の水資源利用学(灌漑学)は、生産性と環境保全とが調和した農学の再構築とその総合化の過程の中で、それと整合性のある体系として再確立する必要があると考えている。
文 献
環境庁「地球温暖化問題研究会」編,1990,地球温暖化を防ぐ,日本放送出版協会.
小谷廣通,1996,遠山明・橋川潮編「環境保全型農業へのアプローチ」 第6章 農地の水管理を考える,富民協会.
---------------------------------------------------------------------------
図1 潅水日、潅水時刻と潅水量
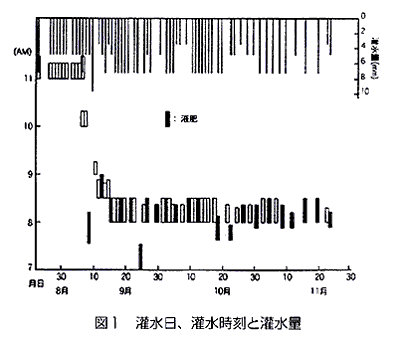
表1 メタン(CH4)と亜酸化窒素(N2O)の年間放出量の推定
(環境庁「地球温暖化問題研究会」、1990より)