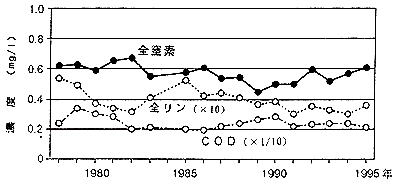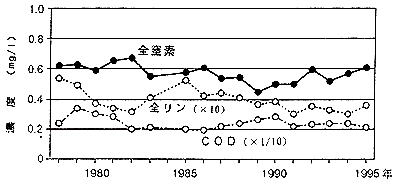
琵琶湖保全は環境学の課題
國松孝男
環境生態学科
1.最近の琵琶湖汚染の特徴
琵琶湖に淡水赤潮が初めて大発生したのは、戦後の高度経済成長期を経た1977年以降のことである。すでに1970年前後から水道水の異臭味問題が起こっており、行政・住民の水質への関心は高まっていた。それが赤潮を契機として県民挙げての運動となり、1979年には「富栄養化防止条例」がわが国で初めて制定された。
その頃から筆者が学生と共に南郷洗堰でモニタリングしている琵琶湖流出水の水質データを示そう。図1をみると、条例制定前後から暫くはリンとCODの濃度に改善の兆しが認められる。しかしそれも1982年ころまでで、それ以降は下水道の整備が進んだにもかかわらず、CODによる汚染はじわじわと悪化する傾向にあり、窒素も1989年までは低下したが、その後かなりのスピードで上昇している。ただし下水道で効率よく除去されるリンは1985年以降ほぼ一貫して低下して来ている。
一方、この間の生物の反応をみると、ウログレナ赤潮は依然として終息していない。それどころかアユが大量に幣死したり、1983年頃から南湖の一部に発生するようになったアオコが一昨年あたりから北湖にまで広がってきた。さらに北湖全域に微少なピコプランクトンが異常発生するようになるなど、生物学的にみた水質は悪化の一途を辿っているようである。
2.琵琶湖汚染と非特定汚染源
水質汚染の進行をくい止めるためには、対策が的外れに終わらないように、慎重に原因を究明しなければならない。滋賀県では、琵琶湖集水域で発生する窒素の38%、リンの68%は家庭や工業などの特定汚染源(点源)から発生していると推定している(表1)。これを根拠にして、これらの特定汚染源からの排水を処理する下水道を水質浄化の切り札として、水質保全施策の要に位置づけてその整備を推進してきた。その結果、公共下水道の整備はこの15年ほどの間に急速に進み、1996年3月末には人口普及率で43%に達し、農村下水道(8.7%)を加えると、滋賀県人口の52%に下水道が普及するまでになった。
下水道によって家庭排水の約半分が処理されるようになり、工場排水の規制が進んだにも拘わらず、期待通り琵琶湖の水質が改善されないのは何故だろう。最も素朴な仮説は、表1で下水道による処理の対象になっていない農業系と自然系すなわち非特定汚染源から、実はもっと多くの窒素やリンが発生しており、そのため下水道による水質改善効果は、表1から期待されるより小さいということである。そうであれば非特定汚染源対策すなわち農業排水対策、森林・林地の荒廃対策、市街地排水対策および流域と湖岸の浄化機能の再生・強化対策などを、下水道整備にも増して強力に展開しなければならないことになる。
この仮説を証明するためには非特定汚染源の汚濁負荷を高精度で調査し、その流出機構を解明しなければならない。実は1984年に滋賀県が主催して世界各地から住民・行政・科学者が集まって開催された第1回世界湖沼環境会議で、すでに非特定汚染源に関する研究の重要性が指摘されていた。ところが逆にその頃からわが国の非特定汚染源に関する研究は、何故か非常に少なくなり、行政による調査もほとんど行われなくなってしまった。そのわけを筆者なりに推定すると、下水道整備など多くの部局ににわたる様々な事業を組み込んだ水質保全施策は一旦回り始めると、その後新たな研究があっても根幹に関わる変更は疎まれるという行政の慣性である。一方、学界ではそれまでの研究が「農業は悪い子でなかった」というところに落ち着いたことから、それ以上の研究意欲をかき立てる動機が乏しくなった。すなわち行政は常に最新の科学の成果に基づいて施策を点検するという当然のことができず、農学研究は農業に免罪符を与えることには成功したが、湖沼水質保全という真の課題にせまる"環境科学の視点"を欠落したまま停滞することになったのである。
3.環境問題を解決するのは環境学
ある学会で土壌肥料学者が、ライシメーター(大型の植木鉢様の実験装置)を用いた畑地からの肥料の流出実験を発表していた。確か5年間にも及ぶ着実な調査であった。ところが彼は「幸いこの間、雨が降っても一度も表面流出は起こらなかった」と安心して見せた。それだけ肥料の流出量が少なくなるからである。それを聞いていた仲間の研究者も安心した。筆者は唖然として何も言えなくなった。大概の川は30・程度の雨でも、中下流では表面排水を受けて濁流になる。彼らはきっと雨の日には川など見には行かないのであろう。この実験は農学研究の実験にはなり得ても、環境科学の実験にはならない。雨が降っても表面流出が起こらないような実験装置は、環境科学の実験装置としては不備であり、すぐに改良しなければならない。5年間もそのまま実験することなど考えられない。
学問にはそれぞれよって立つ基盤がある。農学の基盤は言うまでもなく農業生産である。そもそもその基盤を危うくするような研究は、内部からは起こりにくい。環境問題を基盤とする学問、すなわち環境学の必然性がここにある。誤解を恐れずに言えば、そもそも農業が可愛い農学から、林業が愛しい林学から、自然がおもしろい理学から、環境問題という課題解決に迫る一連の研究は生まれにくいというのが筆者のこれまでの経験である。
4.水田の環境科学−一例として
農地は琵琶湖集水域の土地利用の19.6%を占め、その90.6%は水田である。表1でこれらの水田から発生する汚濁負荷量を計算するのに用いられた数値・原単位(全窒素14.4、全リン0.57kg/ha/年)は、実に1970年前後に行われた調査・研究を基にしており、近年の水質化学のレベルからみれば著しく信頼度が低い。
そこで筆者らは1987年から約3年かけて甲西町正福寺の12haの水田地域で精密な調査・研究を行うことにした。その結果、基盤整備が完了し、用排水分離されているこの地域の水田は、1ha当たり1年間に窒素は45.7kg、リンは8.72kgも排出していることを実証した。すなわち滋賀県が使っている原単位より窒素が3.2倍、リンでは実に15倍も大きい。これらの値を原単位として汚濁負荷発生量を計算し直すと、表1の右に示したように、窒素では31%、リンでは実に47%を農業系が占め、先の仮説通りの結果になった。
琵琶湖流域に広がる49,000haに達する水田の土壌や地形・地質、水管理や肥培管理、農業用水の水質などの立地条件は地域によって大きく異なっている。そのため水田の汚濁負荷発生量にも実際にはかなりの幅があると推察される。従って、琵琶湖集水域の水田を幾つかのタイプに分類し、それぞれ典型的な水田についてさらに精密な調査・研究が必要であることを強調してきた。さらにそれらの成果を展開させ、汚濁削減技術の開発のための基礎研究が要請されている。
参考文献 「農業と環境」久馬一剛・祖田修編著,富民協会, (1995).水情報,14(6),3-6, (1994).滋賀の環境・水質編,滋賀県,p.15,(1994).
---------------------------------------------------------------------------
表1 琵琶湖集水域の汚濁負荷発生量(1990年推計)
| 発生量・発生源 | 滋賀県 | 國松試算 | ||
| 窒素 | リン | 窒素 | リン | |
| 発生量(トン/日) | 24.1 | 1.73 | 28.7 | 2.94 |
| 家庭系(%) | 24.1 | 34.1 | 20.2 | 20.1 |
| 工業系(%) | 19.9 | 39.9 | 16.7 | 23.5 |
| 農業系(%) | 18.2 | 9.2 | 31.4 | 46.5 |
| 自然系(%) | 37.8 | 16.8 | 31.7 | 9.9 |
図1 琵琶湖から流出する湖水の水質