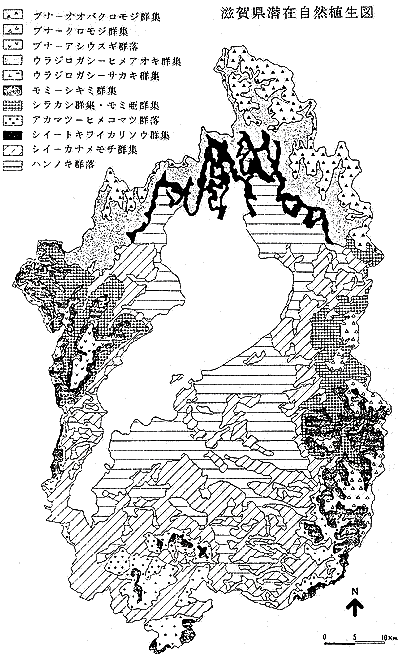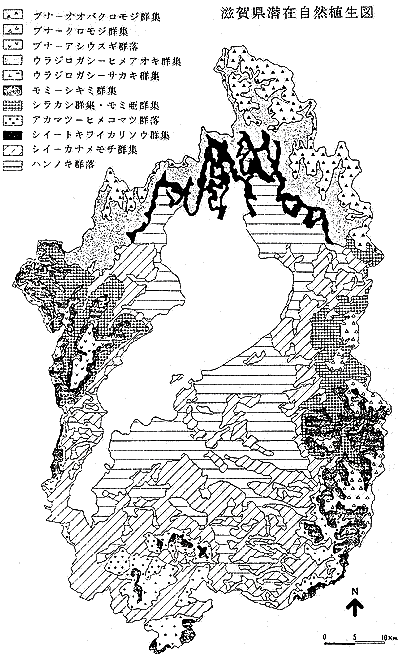
植物社会学と植生環境
小林圭介
環境生態学科
植物社会学は、植生と群落の秩序・法則性を研究する環境学の一分野である。植生は土地に密着して成立し、その立地に適応し、その条件を反映して存在すると同時に、それを改変する。立地と切り離しては、植生を理解することはできない。つまり、植生は環境を指標し、種々の環境要因の総合的効果を映し出す鏡である。同じ種類の植生は同じような構造や機能をもつとともに、同類の総合的環境のもとに成立する。いいかえれば、植生の違いは環境の違いを意味していることになる。
こうした植生に関する自然科学的研究のなかで、特に研究法の一貫性と成果の高さにおいて広く適用され、1950年代以降の新しい植生研究の展開のなかにおいても、一層充実した研究成果を生み出してきたのがZ?rich-Montpellier学派の植物社会学である。この植物社会学は、小地域的な詳細な植生研究から、大地域的さらに大陸間の植生比較研究と集大成にまで、一貫した基準、すなわち種組成に立脚して適用されうる優れた研究戦略をもっている。
植物社会学の重要な概念の一つは、植物の種の生態に関する概念である。種には生態的に広範な分布をする種もあれば、特定の群落に限定される種もある。植物社会学においては、究極的には特定の群落に結びつく標徴種を抽出することにある。種と群落および立地との結びつきの関係は、植生研究一般、さらに種の進化にも関連した基本的な課題であり、植生の典型像を追求する植物社会学においては、標徴種がその研究戦略の根幹をなす。一方、植物群落の基本単位は群集とよばれる。それは、植生資料群の相互比較によって標徴種と同時に抽出される。この「標徴種・植生単位同時抽出」はZ-M学派の植物社会学の研究戦略の特色であり、一種の漸近法である。抽出された群集に内部的な種組成の変異があるときは、識別種が抽出されると同時に下位単位に区分される。また、基本単位である群集は、上位の標徴種によって上位の植生単位に統合される。Z-M学派の植物社会学が小地域的な植生研究から大陸間の植生比較研究にまで適用しうるのは、標徴種概念と種組成に基づく植生単位のヒエラルキー体系化という特色的な研究戦略にある。
これまでの、具体的な調査研究成果についてみると、まず一つは1971年以来、滋賀県の山地部から平野部、湖岸にかけて発達している多様な植生の解明をねらいとして、3,000点以上に及ぶ膨大な植生調査資料を収集し、諸種の植物群落の体系化を行なってきた。その結果、新たに記載された植生単位11群集を含む60以上の植生単位を抽出して、滋賀県の植生誌の解明をほぼ完了している。
他の一つは、日本の高山帯に広く分布するハイマツ群落の広域的な体系化である。北は北海道の利尻島から南は南アルプスの光岳まで、1962年から7年間にわたる現地踏査の結果多くの植生調査資料の収集を行なってきた。また同時に、日本の植生研究の礎を築いた一人である故北海道大学館脇操名誉教授やソ連の林学の研究者が樺太やシベリア地域において報告したハイマツ群落に関する貴重な文献資料も収集した。これら多くの資料によって、植物社会学的概念と手法に基づいたハイマツ群落の分類体系が、初めて確立された。
Z-M学派の植物社会学的研究を越えて、もう一つ重要な植生概念がある。植生は古今不動のものではなく、変貌して現在にいたっている。特に、氷河期以後の変貌の大きな原因としては、人間が耕地を開いたり、薪炭を採取するなどの人間の行為があった。したがって、現在の植生が過去の植生と同一ではあり得ない。しかし、農耕時代以前の植生は、人間によって大きく改変させられることのない、自然条件に適応した植生が存在していたのは間違いない。この人為が及ぶ直前に存在していた植生は、原植生とよばれる。これに対して、現在我々が直接に踏み込んで調べることのできる植生は、現存植生とよばれる。現存植生は、自然条件に適応した構造と種組成をもつ自然植生と、人為によって、自然植生が置きかわり人為のもとでのみ成立、維持されている代償植生から成り立っている。もし、この代償植生に加えられている人為を停止したとき、その代償植生の立地が支え得る理論上の自然植生を潜在自然植生という。
こうした植生の具体的広がりを平面図に示したものを植生図という。特定の環境のところに特定の群落が成立するということから、植生図を通じて環境に関する諸情報を読み取ることができる。それは気候条件や立地条件のみならず、人為的影響や動物の影響などとも関係し、また群落の遷移とか地史にも関係している。理想的に作成された植生図は物理化学的手法により測定してつくられた環境地図よりも、一層正確な環境地図として利用しうるものである。植生図の用途は非常に広範であり、その利用は基礎的なものから応用的あるいは実際的なものにまで及んでいる。例えば、生態学的諸研究の基礎図として用いられたり、地形学、地理学、土壌学、地質学などの多くの分野で利用されている。応用的利用としては、農業や林業を営むにあたり、群落の立地指標性に基づいて、植生図から土地の生産力や適当な農作物あるいは植林樹種などを知ることができるし、農地や牧野の改良法や管理法の手がかりも知ることができる。最近では開発が急速にすすむにともなって、自然との共生が切迫した問題として提起されるようになったが、植生図により環境を総合的に把握して、この問題に対処するようになってきた。
この科学的操作によって抽象化された植生単位の具体的な広がりや配分を地図上に描いた植生図に関係する研究成果のなかで、特に5万分の1の滋賀県現存植生図(1981)と10万分の1の滋賀県潜在自然植生図(1991)は、その精度の高さ、優れた技術と手法などの点で完成された植生図として高く評価されている。したがって、滋賀県における全ての「環境影響評価準備書」のなかに必ず引用されたり、また滋賀県の自然保護計画、緑化基本計画、農村整備計画、地域環境管理計画などの各種計画の基礎図や基礎資料ともなっているし、その利用は広範かつ多方面にわたっている。そのほか、多くの市町村や地域レベルでの現存植生図や植生自然度図、潜在自然植生図の作成も行っている。
---------------------------------------------------------------------------